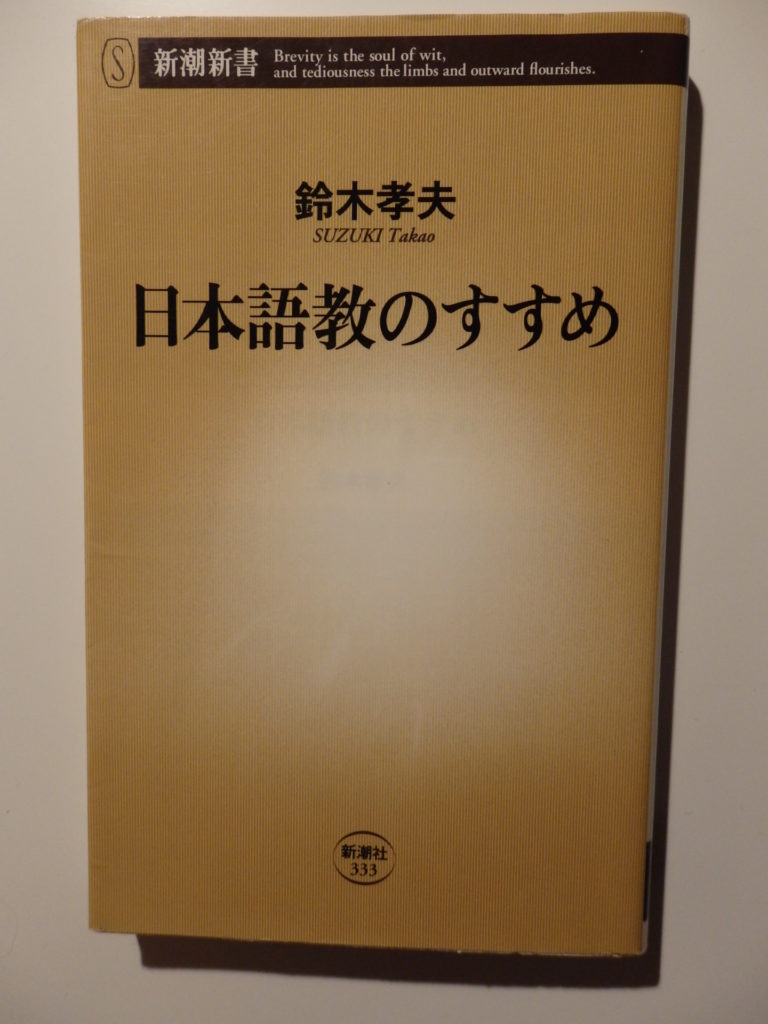
「日本語は英語に比べて未熟で非論理的な劣等言語である」—– 明治維新の頃、日本語をやめて西洋の言語を国語として採用しよう、という動きがあったのをご存知ですか? あるいはそんなことを勉強したのを覚えていますか?
著者・鈴木氏はこの本で、日本語のことを礼賛しています。日本語が世界の大大言語のひとつであることを第一の理由にあげ、日本人は自国語にもっと誇りを持つよう叱咤激励しているのです。
日本の初代文部大臣・森有礼(ありのり)が、まず英語を国語にしようと主張しました。また大文豪・志賀直哉はフランス語を国語にすべきだと真面目に提案していました。
他にも、漢字をやめてアルファベットで表記した方が良い、など、数多の意見が噴出したそうです。
今でも、子どものうちから英語を学ばせて、我が子をバイリンガルに育てたい、という親は多勢いて、英会話教室は花盛りですが、果たして日本語はそれほど卑下される言語なのでしょうか?
大大言語という言葉に戻りましょう。世界には約6000種類の言語があると言われていますが、そのうち使用する人の数が1億を超える大言語は10前後しかありません。そして日本語は立派にこの10前後の中に入っている、使用者の多い言語なのです。
また、公用語と母語というのは、かなり違います。バイリンガルとは母語を2つ持っているように思われがちですが、完全に二つの言語を自由に操るという人はまれで、大抵は母語がその人の思考や思想に強く影響します。
ちょっと私の得意なドイツ語で考えてみましょう。
ドイツ語の数字は少しひねくれて(?)います。二ケタの数字を言う時、一の位を言ってから、十の位を言うのです。英語で言った方が通りがいいと思うので、例えばこうなります。
21は「ワン アンド トゥエンティ」、63は「スリー アンド シックスティ」
なんとまあ不便であることか。私は暗算はドイツ語ではできませんし、ドイツで支払いの時には、しょっちゅう間違えます。私のドイツ語力に問題があるわけですが、ドイツ語の数字がこのように不可解(?)な順番で言うことにも理由の一端があると言えるでしょう。
数字だけでも計算に多大に影響するのですから、言葉が違うということは、考え方の根本から変わってきます。母語と公用語が違うということは、別々の思考が一人の人間の頭の中にあるということです。
日本語だけで考えてみても、ちょっと想像がつきます。わかりやすい例が方言です。「しんどい」という言葉は、今ではすっかり全国民に定着したかにみえますが、おそらく関東の方には、話すのに抵抗があるのではないでしょうか? 大阪人が「しんどい」と言うのと、東京人が「疲れた」というのは、意味は同じでもニュアンスが微妙に違ったりします。
ちょっと本の話からそれてしまいました。「日本語教のすすめ」は日本語がいかに素晴らしい言語であるか、この素敵な言語をもっと世界に広めよう、というような趣旨のことが、たくさんの分かりやすい例を取り上げて、書かれています。
日本語を外国人に教えるにあたって、自国語に自信を持つ、私には良書となりました。日本語に対して懐疑的な方、英語がなかなか身につかないと悩んでおられる方、ぜひ、この本を読んでみてください。きっと納得のいく答えが見つかるはずです。