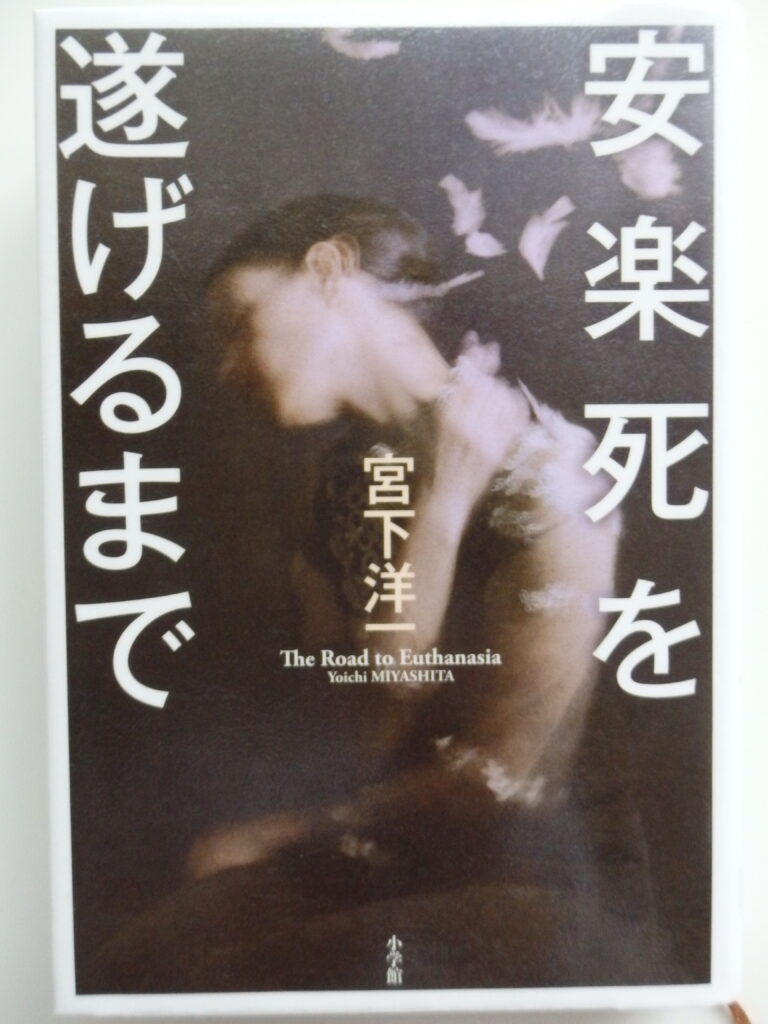
「安楽死を遂げるまで」2017年12月初版の単行本。そして
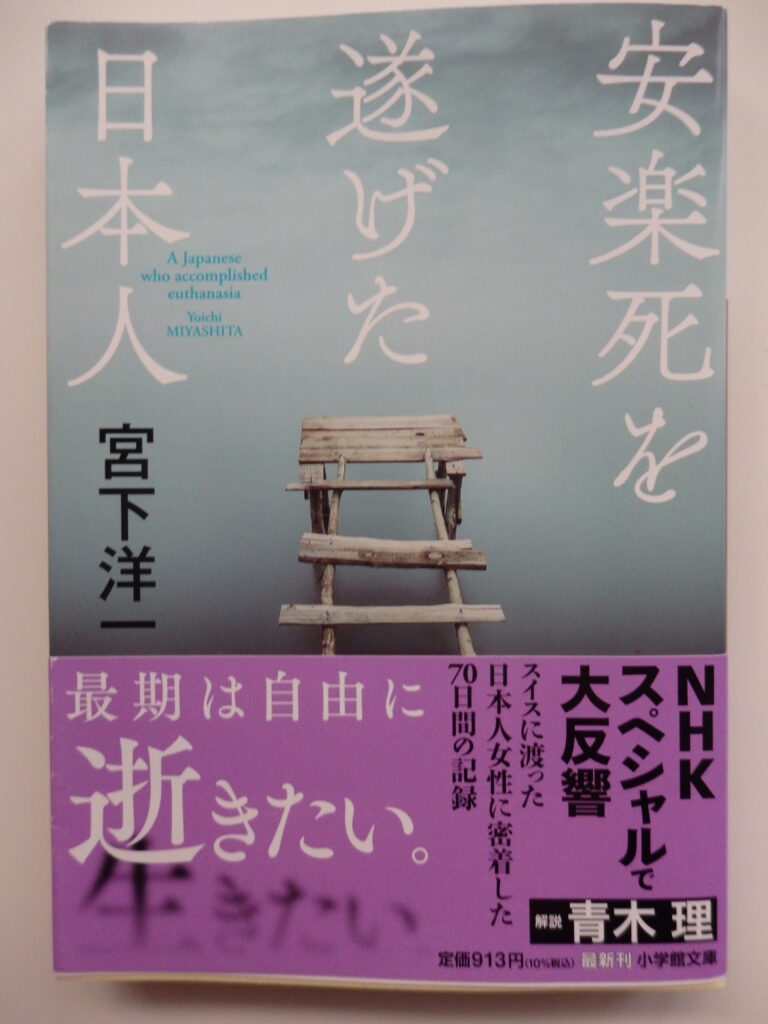
2021年7月初版「安楽死を遂げた日本人」が文庫本。
ずいぶん短い間に宮下氏は重いテーマを精力的に書かれたのですね。世界をまたにかけた数々の取材・インタビュー、各国の法律の詳細など、安楽死に関する興味が満たされる(?)内容です。
そもそも「安楽死」と「尊厳死」の違いからしてよくわかっていない私にとって、この本の丁寧な解説はとても理解しやすく、2冊を誤解なく読む上でも大事なベースとなりました。
講談社ノンフィクション賞を受賞した「安楽死を遂げるまで」は世界6か国の《命の現場》を取材したルポタージュ。著者・宮下氏はバルセロナに拠点を置き、看護師のスペイン人パートナーから安楽死を肯定する発言を何度も聞かされたことが、このテーマに取り組むきっかけとなったようです。
1冊目は、欧米人の安楽死の現場に立ち会ったりインタビューをしたりで、宮下氏の肩にものすごく力が入っている印象を受けましが、2冊目は、取材対象者が日本人だったためか、とてもナチュラルな文面という感想を持ちました。
どれほど長く海外で暮らし、異国人パートナーと生活を共にしても、宮下氏の宗教観というか「死」のとらえ方は、あくまでも《日本的》なんだなあ、と「安楽死を遂げた日本人」を読むとじわじわ感じました。
NHKスペシャルは観ていないので、大反響は存じ上げないのですが、小島ミナさんの最期は、その難病から推測する限り、私にとっても憧憬であり理想です。
日本で安楽死を認める法律ができる可能性が限りなくゼロに近いことは、青木理氏が文庫本の解説でうまく書いていらっしゃいます。日本の政治家で重鎮の方々の人権に関する知識というか見識があまりにお粗末なのが、情けないやら滑稽やら。
日本人の横並び意識の強さは、「個」を大切にする欧米人の考え方と根本的に異なり、自殺ほう助というナーバスな問題を抱える《安楽死》を容認することはないでしょう。
もちろん難病を抱え、この痛み・辛さから逃れる手段は「死」しかない、という考えは、個人的には理解できます。ただ日本人の同調圧力の強さを帰国後、改めて認識した、あまり優秀でない私の脳みそで推測すると、安楽死を法律で認めることのリスクはあまりに高い・高すぎる、とハザードランプが不気味な点滅を始めるのです。
私が父の最期を看取ったことは、果たして理にかなったことだったのか。この2冊を読みながら、何度か自問しました。平均寿命を超えた比較的高齢であったこと、認知症を患う前にリヴィングウィルに近い死生観などを直接確かめたことがあったこと、理解ある医師のおかげで自宅で看取ることができたこと。父は最後まで穏やかな顔だったので、間違ったことはしていないと思うのですが。
「胃ろうをつけてまで長生きしたい? 口から食べられなくなったらどうしたい?」これって誘導尋問というか、無理やり延命拒否を言わせるようにしむけていたのかなあ。
安楽死とは少し観点がずれたかもしれませんね。日本人は「死」をテーマに話し合うことを忌み嫌う傾向が強いですが、私はこのGW、母としっかりリヴィングウィルについて話し合おうと思っています。