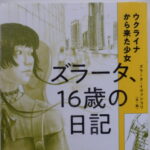
ウクライナから来た少女 ズラータ、16歳の日記
ウクライナの紛争地域の様子が迫真する、16歳の少女の日記。奇遇なことに、少女の興味の対象は日本語と日本のマンガで、強運な彼女は、戦地から脱出し、夢見た国への切符を掴みます。私の16歳当時は、幼かったよなあ。ズラータさん、応援してます!
愛してやまない本のこと、言葉のこと、そしてドイツに関することを綴ったブログです。
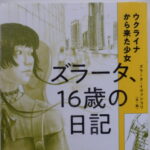
ウクライナの紛争地域の様子が迫真する、16歳の少女の日記。奇遇なことに、少女の興味の対象は日本語と日本のマンガで、強運な彼女は、戦地から脱出し、夢見た国への切符を掴みます。私の16歳当時は、幼かったよなあ。ズラータさん、応援してます!
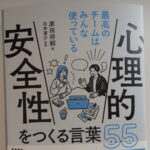
いつものひと言を変えることで、会話が増え、ポテンシャルがあがり、チャレンジが始まる。すると組織が活性化していく。多くのリーダーが安易に使っている言葉が、実は士気を下げたり、ただ困惑させるだけの言い回しであることを理解できる良書です。
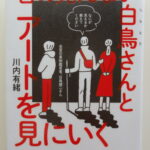
絵画や彫刻など、およそアートという範疇で才能が皆無の私は、美術館や博物館で作者に対するリスペクトなどなく、「あ、これ好き!」となれば、ず~~~っと前に陣取り、他の作品は素通りする、大変身勝手な見物人でした。白鳥さんとご一緒させていただいて、改心したいです。

外国の伝統食とかソウルフードという文字を見ると、どうしても食べたくなる好奇心の強い食いしん坊な私。新聞記事で教え子たちの懐かしの味を知り、尋ねると、律義な生徒がプレゼントしてくれて・・・クメール語騒ぎは、図書館の偉大さ発見につながりました。

アルツハイマー病を治す奇跡の細胞「フェニックス7」。再生医療は救世主か、それとも悪魔か? 山中伸弥教授のiPS細胞は、その後どんな風に発展しているのか? 医療の繊細な部分と崇高な部分。警察と国家権力の正義と打算。様々な考えが錯綜します。

14歳のヤングケアラーの小説は、ブレイディみかこさんが実際に目にした、限りなくリアルに近い創作なのでしょう。おそらく著者は、大評判になった「ぼくはホワイト・・・」より、こちらの世界を世に問い、訴え、変えたい、というのが本音ではないかと想像します。

住み慣れた東京石神井から博多湾に浮かぶ離島・能古島へ。事件にぶつかりながらも笑顔でかわし、自家菜園で採れる収穫物を愛でながら、いそいそとキッチンに立つハルコさん。老後の指南役に手元に置いておきたい、素敵な本です。
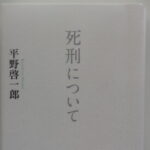
死刑が必要だという心情は、実は時代劇やヒーローものによって操作された感情かもしれません。犯罪を犯さざるを得なかった被告の生い立ちを慮り、犯罪そのものを根絶する社会の必要性が、この本では静かに訥々と語られています。
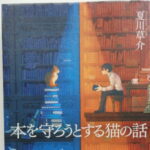
「お金の話はやめて、今日読んだ本の話をしよう」。本の話。いいですね。明日・秋分の日は、母と電車で京都へお墓参りに行きます・車中で読む本は、既に準備OK。次回も、その次も、その次の次も、違う本をテーマにたくさんお喋りできますように。
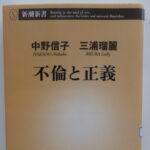
世に不倫は多くあります。これだけ断罪されている芸能人が次々に現れても、消えることはありません。愛なら許されるのか、理が勝つべきなのか。脳科学者と国際指政治学者が、それぞれの得意分野で、結婚の真実を語り尽くしています。